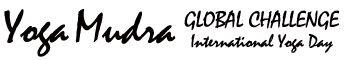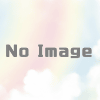個人の変容から社会の変化へ——「いかしあうつながり」で紡ぐ再生型コミュニティの実践
ヨガムドラは、ギフトエコノミーと優しさの循環を軸に、ヨガにまつわる学びと出会いの場をひらいています。
ここでのインタビューでは、その軸に心から響いたひと・もの・こと・活動をたどり、分かち合います。
はじめに——内なる気づきが社会を変える原動力に
2025年7月、仕事で滞在していたバリ島・ウブドで、知人がNPOグリーンズの「リジェネラティブデザインカレッジ」の合宿の一コマとしてブレスワークのセッションを担当することに。
私は流れでアシスタントとして同席。
そのご縁で、NPOグリーンズ事務局長の小倉奈緒子(なおこ)さんに、団体の活動や「いかしあうつながり」についてお話を伺う機会を得ました。
まず現場で体感することがいちばんの学び。体験が先に立つと、言葉や関係性が変わっていく
なおこさん・要旨

本記事では、なおこさんから伺った言葉と、現地で感じた空気、公式情報を織り交ぜ、NPOグリーンズさんについてご紹介します。
私たちの日常の小さな気づきが、どのようにして社会全体の変化へとつながっていくのでしょうか。
朝の瞑想で感じる心の静けさ、自然の中を歩きながら得る直感、オーガニック食材を選ぶときに湧き上がる価値観 -これらは決して個人の内側だけに閉じた体験ではありません。
「いかしあうつながりがあふれる幸せな社会」を目指すNPOグリーンズは、まさにその橋渡しを実践している団体です。
2006年の設立以来、環境問題や社会課題に取り組む人々を応援し、つなげ続けてきた同団体のミッションは「個人の変容と実践を応援する」こと。
そして「生きる、を耕す。」という合言葉には、一人ひとりの内的な成長が、やがて土壌を豊かにするように社会全体を再生していくという深い洞察が込められています。
今、私たちが直面する気候危機や格差拡大といった課題は、従来の「持続可能性(サステナブル)」を超えた「再生型(リジェネラティブ)」なアプローチを求めています。
それは単に現状を維持するのではなく、壊れた関係性を修復し、より豊かな循環を生み出すことです。
グリーンズが実践する「いかしあうつながり」の本質
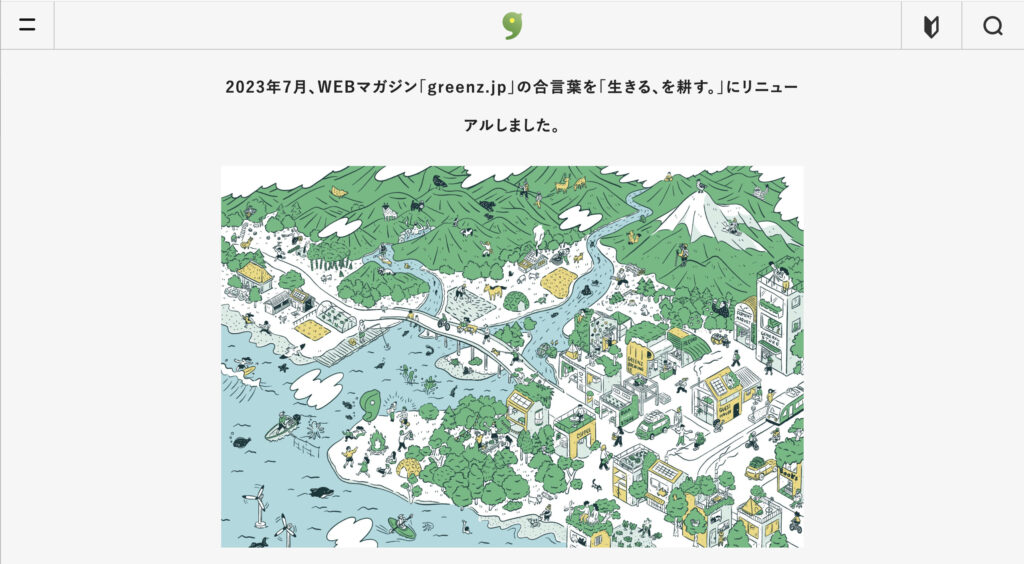
グリーンズの合言葉の「生きる、を耕す。」や、提唱する「いかしあうつながり」は、競争や搾取を前提とした従来の社会システムに代わる、相互扶助的な関係性の在り方を示しています。
これは経済学者ケイト・ラワースが描く「ドーナツ経済学」や、先住民の智慧に根ざした「すべてはつながっている」という世界観と深く共鳴します。
なおこさんによれば、同団体の仕事の重心はBeing(あり方)にあります。
どう在るかがどう関わるかを変える -その前提で関係性の再設計を進めている、という視点でした(要旨)。
具体的には、一方的な支援ではなく、それぞれが持つ異なる能力や資源を活かし合う相互的な関係を築くこと。
環境活動家と農家が協働し、デザイナーと地域住民が一緒にコミュニティスペースを作り上げ、起業家と研究者が新たなソリューションを生み出していく -そんな多様性を力に変える仕組みづくりです。
この理念は、グリーンズが運営するWebマガジン「greenz.jp」でも体現されています。
環境や社会にまつわる課題を単に問題として報じるのではなく、それらに創造的に取り組む人々の物語を通じて「自分も何かできるかも」という希望と行動への意欲を育んでいます。
学び・働き・つながりを有機的に循環させる仕組み

NPOグリーンズでは、「greenz.jpの記事を読んで、「自分も何かしてみたい」と思った方には変容プロセスに寄り添う3つの入り口が構成されています。」
学びの場:グリーンズの学校
単なる講座提供ではなく、参加者が自分なりの実践を見つけられるよう設計されたラーニングコミュニティです。
現在NPOグリーンズでは、リジェネラティブデザインカレッジとローカル開業カレッジが開かれています。
コミュニティーでは多様なプログラムを通じて、参加者は理論と実践を往復しながら、自分らしい社会貢献の形を探求します。
重要なのは、講師から一方的に知識を受け取るのではなく、参加者同士の対話や振り返りから学びを深めていく相互学習のスタイルです。
働く導線:WORK for GOOD
「働く」を通じて社会を変えたいと願う人々のためのキャリアプラットフォームです。
従来の求人サイトとは異なり、企業のパーパス(存在意義)や社会的インパクトを重視した仕事情報を発信。
環境再生型農業、循環型経済、コミュニティ活性化など、未来志向の事業に携わりたい人と組織をマッチングします。
単なる転職支援ではなく、働き手の価値観と仕事の意味を深く結びつけるキャリア形成を支援しています。
コミュニティ:つながりの土壌づくり
学びと実践を支える基盤として、グリーンズの学校の卒業生や寄付読者制度、イベントを通じたコミュニティが機能しています。
ここでは参加者が「ともに生かし合う仲間」として、役割を柔軟に行き来しながら、互いの変容を支え合います。
卒業後は、自発性が芽を出せる“土壌”を整える。
外側から企画を与え続けるのではなく、卒業生コミュニティの中で仲間同士が自発的な動きを生み出し、互いに刺激を受けながら育んでいくことが、その継続性を支えています。
なおこさん・要旨
多様性を前提とした「関わり方」のデザイン革命
グリーンズの実践で注目すべきは、参加のハードルを下げるための価格設計です。
基本は主催側が設定する定価制ですが、プログラムによっては「学生・社会人20代」「社会人30代以上」といった区分料金があり、立場に応じて無理なく参加できるよう配慮されています。
「“モノを売る”というより、その場を共につくるためのサポート費に近い感覚です。
安心して関われる価格設定が、関係を続けやすくしているのだと思います」(なおこさん・要旨)
こうした仕組みは、環境問題や社会課題にもっとも切実に関わる層の声と知恵を社会変革に活かすためにも重要です。
多様な背景を持つ人々の参加を促し、包摂的で効果的な解決策の創出を可能にしています。
リジェネラティブデザインカレッジ——環境再生の学び舎
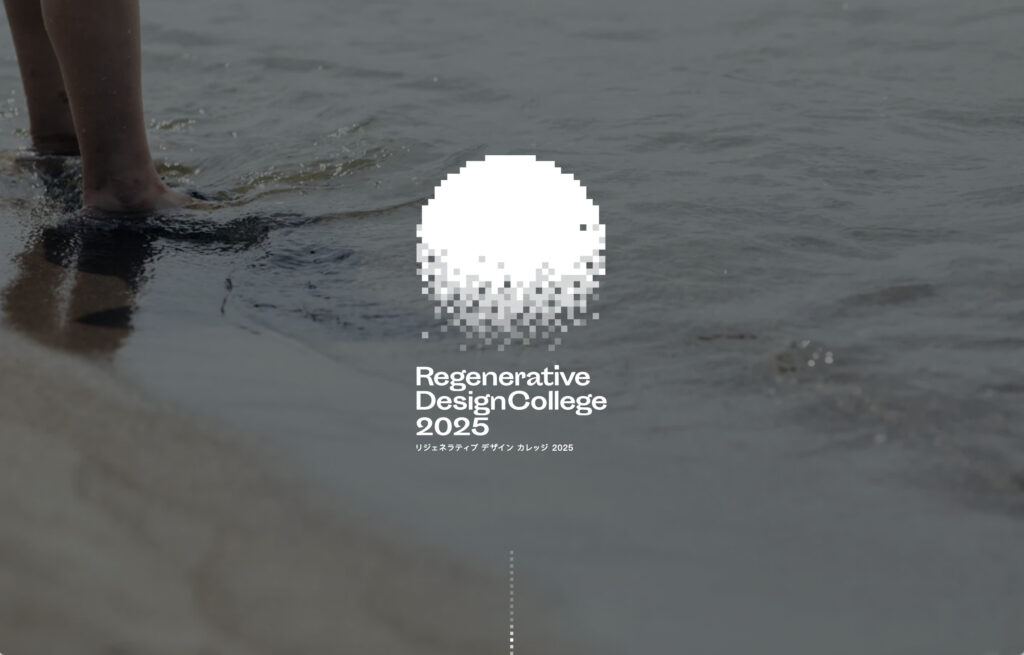
グリーンズが主催する「リジェネラティブデザインカレッジ」は、環境再生への理解と実践を深める約4ヶ月間のプログラムです。
リジェネラティブ・デザインの思想を基に、講義、ゼミ、フィールドワーク(森の再生現場や農場での実習など)を通じて学びを深めます。
リジェネラティブデザインカレッジの肝は“まず現場に行くこと”。
体験を先に置き、言葉はその後に整えるという設計思想だと、なおこさんは位置づけていました(要旨)。
プログラムの特徴は、生態学的思考と社会システムデザインを同時に習得できること。
参加者は農業、建築、教育、ビジネスなど様々な分野から集まり、それぞれの専門性を活かしながら最終発表に向けて取り組みます。
これにより、分野を超えた革新的なアイデアが生まれやすい環境が整っています。
サステナブルを超えるリジェネラティブな生き方とは
従来の環境配慮が「これ以上悪化させない」ことを目標とするなら、リジェネラティブなアプローチは「より良い状態に再生する」ことを目指します。
これは単に環境技術の問題ではなく、私たちの生き方や関係性の根本的な見直しを意味します。
例えば、オーガニック農業においても、単に化学肥料を使わないだけでなく、土壌の微生物叢を豊かにし、炭素固定を促進し、地域の生態系全体を活性化させる実践が求められます。
また、コミュニティづくりにおいても、問題を解決するだけでなく、住民同士の信頼関係を深め、地域の文化的多様性を育み、次世代により豊かな社会を残していく視点が重要になります。
この転換には、西洋近代の「支配・管理」的思考から、先住民や東洋の「共生・調和」的思考への学び直しも含まれます。
自然を征服する対象ではなく、私たち自身もその一部である生命のネットワークとして捉え直すことで、真に持続可能な社会への道筋が見えてきます。
実践から実践へ——今日から始める5つのステップ

- 自分の価値観を明確にする
何を大切にして生きているのか、どんな世界を次世代に残したいのか。週に一度、静かな時間を作って自分自身と対話してみましょう。 - 地域のつながりを深める
地元の農家市場、環境活動グループ、まちづくり団体などに参加し、同じ価値観を持つ人々とのネットワークを築きます。 - 学びの場に身を置く
グリーンズの学校のような、実践的なラーニングコミュニティに参加。一人では続けにくいことも、仲間がいれば継続できます。 - 消費から創造へ
単に環境に良い商品を買うだけでなく、DIY、アップサイクル、シェアリングなど、創造的な実践を日常に取り入れます。 - 小さな実験を続ける
完璧を目指さず、失敗も含めて学びながら、自分なりの持続可能な暮らし方を実験していきます。
おわりに——変容の波紋を社会へ

一人ひとりの内なる変化が、家族、職場、地域、そして社会全体へと波紋のように広がっていく。
グリーンズの実践は、その可能性を具体的な形で示してくれています。
環境問題の解決も、社会の再生も、結局は私たち一人ひとりの意識と行動の変容から始まるのです。
まとめると、小さく試し、対話し、現場で確かめる——その往復が、グリーンズの実践を支えています
なおこさん・要旨
「生きる、を耕す。」という言葉の通り、私たちの人生そのものが、より良い社会を育む畑なのかもしれません。
今日という日から、あなたなりの「いかしあうつながり」を築いてみませんか。
NPOグリーンズ(団体について)
greenz.jp HP:https://greenz.jp/about/
リジェネラティブ・デザインカレッジ:https://regenerative-design.college/